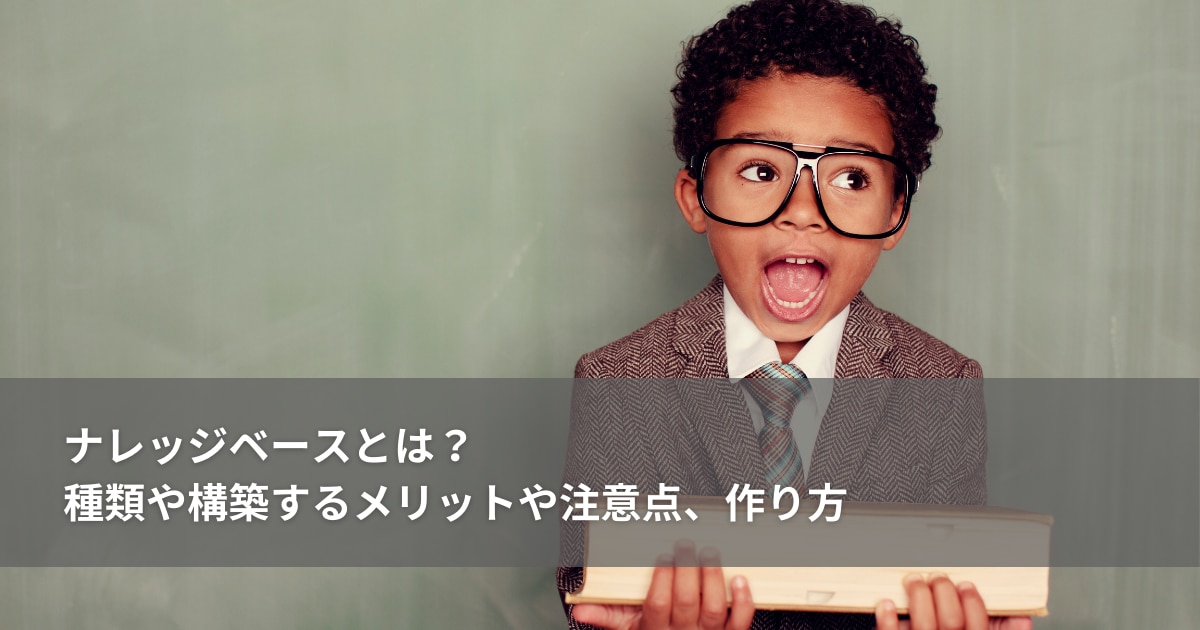
ナレッジベースとは?種類や構築するメリットや注意点、作り方
※この記事はディー・キュービック株式会社のコラムより移行したものです。 |
社内の知識を十分に活用できていないという課題は、「ナレッジベース」によって解決できる可能性があります。近年のビジネスシーンでは、社内のあらゆる知識を組織的に蓄積し、活用する「ナレッジマネジメント」が注目されています。そこで役立つのが、データベースとしての機能を有するナレッジベースです。
この記事では、ナレッジベースの基礎知識をご紹介します。また、ナレッジベースのメリットや注意点、構築方法もお伝えするため、ご担当者様はぜひ参考にお読みください。
目次[非表示]
- 1.ナレッジベースとは?
- 1.0.1.あわせて読みたい
- 2.ナレッジベースの種類
- 2.1.データベース型
- 2.1.1.【サービスの例】
- 2.1.1.1.■Confluence
- 2.1.1.2.■esa
- 2.2.データマイニング型
- 2.2.1.【サービスの例】
- 2.3.社内wiki型
- 2.4.グループウェア型
- 2.5.ヘルプデスク型
- 2.5.1.あわせて読みたい
- 2.5.1.1.■OfficeBot
- 2.5.1.2.■Zendesk
- 3.ナレッジベースを構築するメリットと注意点
- 3.1.ナレッジベースのメリット
- 3.2.ナレッジベースの注意点
- 4.ナレッジベースの作り方
- 4.1.目的やターゲットを明確にする
- 4.2.ナレッジベースの種類やツールを選択する
- 4.3.ナレッジベースの内容や構成を決める
- 4.4.ナレッジベースの運用や改善を継続する
- 5.ナレッジベースで社内の知識を有効活用しましょう
- 5.0.1.あわせて読みたい
ナレッジベースとは?
ナレッジベースとは、社内の有益な情報や付加価値のある経験・知識を集約し、検索や活用ができる状態にまとめたデータベースです。「知識ベース」や「ナレッジデータベース」とも呼ばれます。ナレッジベースは、組織内のナレッジ共有によって技術力や生産性を高めるナレッジマネジメントを推進するシステム・ツールとして機能します。ナレッジマネジメントについて詳しくは以下の関連記事で解説しているため、こちらもぜひお読みください。
あわせて読みたい
ナレッジマネジメントとは?導入する目的やメリット、手法、注意点
ナレッジベースの種類
ナレッジベースにはさまざまな種類のツールがあり、それぞれ特徴や活用シーンが異なります。自社の業務課題に適したナレッジベースの種類を見極めましょう。 
データベース型
データベース型のナレッジベースは、社内の情報を蓄積し、共有できるのが特徴です。蓄積されたデータは必要に応じて検索することで活用できます。データベースとしての情報の整理や管理に長けている一方で、データ分析や課題の発見には向いていない傾向にあります。
【サービスの例】
■Confluence
<特徴>
- Atlassian製の製品であり、他のツールとの連携が容易である
- ページの階層が明確で、構造化されたドキュメント管理が可能
- マクロやテンプレートが豊富で、多様なドキュメントニーズに対応
<弱み>
- UIがやや複雑で、初心者には使いにくい場合がある
■esa
<特徴>
シンプルで直感的なUI設計で使いやすい
Slackなど他のツールとの統合機能が提供されている
タグやカテゴリー分けが柔軟で自由度が高い
<弱み>
- 無料版がなく、全てのプランが有料
<特徴>
シンプルなUIで使いやすさを重視している
ノートの共有が簡単にできるためチーム内コミュニケーションがスムーズ
タスク管理機能を組み込んでいるため、情報管理と仕事の進捗を一元管理可能
<弱み>
- 比較的新しいサービスのため、情報や実績が多くない
データマイニング型
データマイニング型のナレッジベースには、大量のデータから有益な情報を見つけ出す、マイニングツールの機能が搭載されています。膨大なナレッジを分析して、ヒントになる情報を発見することが可能です。データの蓄積や共有よりも分析を得意とし、経営戦略やマーケティング施策の立案に適しています。
【サービスの例】
<特徴>
- 管理しているドキュメント群の中から、AIが参考となるドキュメントをピックアップしてユーザーにお知らせ
- 操作性が快適でブラウザでの検索と同じ感覚で可能
- 豊富なデータ整理・分析機能を備える
<弱み>
- 初心者にはやや使いづらいと感じられるインターフェース
社内wiki型
社内wiki型のナレッジベースは、百科事典のような形式で社内の情報をわかりやすくまとめて共有できます。なお、「wiki」とは不特定多数のユーザーが共同で編集して知識を集めるタイプのWebサイトの仕組みを指します。そのため、社内wiki型を有効活用するには従業員による積極的な投稿が不可欠です。
【サービスの例】
■NotePM
<特徴>
直感的なユーザーインターフェース
マークダウン記法に対応しているため、技術寄りのユーザーに適している
変更履歴が自動記録されるため、ナレッジの変遷を容易に確認可能
<弱み>
- 他のサービスと比べると、複数ユーザー間の同時編集機能に劣る
■Qast
<特徴>
質問と回答を中心に構築されたナレッジの共有・検索が得意
ソーシャル機能が充実している
ダッシュボードでナレッジの活用状況を定量的に把握できる
<弱み>
- 他のドキュメント管理機能には限界がある
■Stock
<特徴>
シンプルで美しいデザインのユーザーインターフェース
チーム内での情報共有に特化している
SlackやEvernoteなどのツールと連携が可能
<弱み>
- 大規模組織には向かない場合がある
グループウェア型
グループウェア型のナレッジベースには、メールやチャットツールといったコミュニケーションの機能が搭載されています。ファイル共有やスケジュール管理を効率化して、社内の連携を強化できるのが特徴です。ナレッジベースと併せてコミュニケーション機能を導入したいケースに適しています。
【サービスの例】
■Garoon
<特徴>
企業向けに設計された多機能なグループウェア
スケジューラやワークフロー管理など幅広い機能を備える
kintoneやMicrosoft 365との連携が可能
<弱み>
- 多機能ゆえUIが直感的ではない
■WowTalk
<特徴>
社内コミュニケーションを強化するチャットやビデオ機能
モバイルに最適化されたインターフェース
無料サポートが充実している
<弱み>
- 外部システムとの連携が限定的
ヘルプデスク型
ヘルプデスク型のナレッジベースは、質問と回答がセットになった一問一答形式でナレッジをデータベース化し、FAQとして活用できます。コールセンターのクレーム対応をはじめとした、マニュアル作成では網羅しにくい業務に適しています。
あわせて読みたい
問い合わせ対応マニュアルの作り方|活用するメリットとポイント
■OfficeBot
<特徴>
- 自動化と生成AIを活用したナレッジ共有
- 細かいニーズに合わせたカスタマイズが可能
- 英語・中国語・韓国語などの多言語に無料で対応
<弱み>
- 高度なカスタマイズには技術力が必要
■Zendesk
<特徴>
- カスタマーサービスとナレッジベースの強力な統合
- スケーラビリティと柔軟なカスタマイズオプション
- 世界10万社以上の豊富な導入実績
<弱み>
- 機能の全てを活用するには高額な料金プランを必要とする場合がある
ナレッジベースを構築するメリットと注意点
ナレッジベースを構築すると、具体的にどのようなメリットが期待できるのでしょうか。また、導入に際してどんなポイントに注意するべきでしょうか。ここではメリットと注意点を解説します。 
ナレッジベースのメリット
ナレッジベースを導入すると、企業内の重要な知的財産を保護するとともに、業務で有効活用できるようになります。暗黙知を形式知に変えて、社内のあらゆるナレッジを一元管理できます。チームや部署間の連携が強化され、効率的な情報共有が可能です。また、リアルタイムで内容を更新できるため、スムーズに最新情報を共有できます。
また、ナレッジベースの導入によって業務効率化や品質向上が期待できます。業務に関する情報がマニュアル化されると、全従業員に偏りなく知見が広まり、属人化が解消されたり問題を自己解決しやすくなったりするためです。さらには、形式知化することで 顧客対応品質の均一化・平準化にもつながります。つまり、ナレッジベースの導入による大きなメリットの一つは社内外を問わずナレッジをムラなく平等に浸透させることが容易になる点です。
ナレッジベースの注意点
社内にナレッジベースを活用する文化を浸透させるには、業務で使用しやすいツールを選定し、環境を整備する必要があります。特に重要となるのは、検索性が優れていて、目的の情報へ簡単にアクセスできることです。検索機能が直観的に操作しづらいと、負担になりナレッジベースが十分に活用されないおそれがあります。
ナレッジベースの作り方
最後に、ナレッジベースを構築する方法をお伝えします。ナレッジベースの運用で成果をあげるために、以下の取り組み方を意識してみてください。
目的やターゲットを明確にする
ナレッジベースを構築する前に、目的やターゲットを明確化しましょう。まずは「カスタマーサポートでオペレーターの応対品質を底上げしたい」「社内手続きのワークフローを効率的に共有したい」といった大きな方向性を決め、プロジェクト内でコンセンサスを図りましょう。その後、どのような情報を可視化するべきか、社内の誰が利用するのか、導入効果をどのように評価するかなどを定めます。評価の際は、利用率や満足度などの指標を設定して測定すると良いでしょう。
ナレッジベースの種類やツールを選択する
ナレッジベースを導入する目的やターゲットに応じてツールを検討します。その際は、ナレッジマネジメントツールを活用する方法と、既存システムを活用する方法があります。
ナレッジマネジメントツールとは、前述のようなナレッジの蓄積や共有に特化したツールのことです。導入時に初期費用や月額費用のコストがかかるものの、検索性や管理性が高く、ナレッジ活用を容易に実現できます。一方、既存システムを活用する場合は、「Excel」や「notion」などをナレッジベースとして利用するのが一般的です。費用を抑えられる反面、専用ツールと比べると検索性が劣り、データ更新の手間がかかりやすいのが難点といえます。
ナレッジベースの内容や構成を決める
ナレッジベースの内容や構成を検討します。シンプルでわかりやすく情報をまとめるよう意識しましょう。内容の例として、FAQ・よくある質問・業務の基礎知識・作業手順・作業のコツ・ノウハウといった項目が挙げられます。これらのナレッジを、見出しやカテゴリー、タグなどを使って分類しましょう。構成はユーザーニーズや検索パターンに合わせて柔軟に変更できる状態が望ましいといえます。
ナレッジベースの運用や改善を継続する
ナレッジベースの運用開始後は、定期的にナレッジの追加や修正を行い、データを最新の状態に保つことが大切です。同様に、定期的にユーザーのフィードバックやアクセス状況を分析し、ナレッジベースの品質や利便性を向上させる必要があります。このほかにも、社内にナレッジの育成や共有をする文化を根づかせ、社員の意識や参加意欲を高める取り組みも実施すると良いでしょう。

ナレッジベースで社内の知識を有効活用しましょう
ここまで、ナレッジベースの基礎知識から構築方法までお伝えしました。従業員が個人的に保有していた知識を組織間で共有する仕組みがあると、属人化の解消に効果的です。社内の連携が強化されたり、業務の引き継ぎがスムーズになったりと、さまざまなメリットが期待できます。ナレッジベースを導入する際はツールありきで進めるのではなく、目的や対象を見定めた導入と、ナレッジベースにかかわる人が積極的に参加する文化の醸成が重要です。属人化の解消や知識の共有にお悩みの方は、一度ナレッジベースの活用を検討してみてはいかがでしょうか。






